免疫機構の成長、発育 新生児期から乳児期、幼児期への成長発育は親にとっては大きな喜びであり、小児科医にとっては大きな研究対象であった。しかしその多くはいまだに謎の部分が多い。しかし近年ライフサイエンスの進歩により徐々にそれが明らかになりつつある。免疫機構における成熟のメカニズムでもその詳細が明らかにされつつある。免疫機構成立の過程解明が免疫機構そのものの解明に他ならず、それが感染防御のみならずアレルギー疾患の病態解明、癌免疫の解明に結びつくと言っても過言ではない。 乳児にアレルギーが多く、それらが成長にしたがって自然治癒に向かうことが知られている。その機序の解明はアレルギー疾患の治療に直結するだけに研究の発展がが期待されていた。最近新生児期から乳幼児期への免疫機構成熟過程の研究が進み、多くのことが明らかにされている。新生児期ではTh1の機能が抑えられている結果、Th2優位に傾き易い傾向があることが知られていたが、その分子レベルでの機序が明らかにされつつある。 新生児期にTh1機能が抑制されているのは妊娠の影響であることが知られている。胎児は父親由来のハプロタイプを持つアロ抗原であり、同種移植のドナーとなっている。その為拒絶反応を抑制する何重もの防御機構が働いている。まず胎盤組織は母親と胎児を隔てる緩衝地帯であり、そのため主要組織適合抗原の発現はゼロレベルに抑えられている。主要組織適合抗原がないとNK細胞の標的となるため、マイナーなクラス1抗原が発現されている。物理的な防御だけでなく免疫学的な防御機構も存在する。拒絶反応の担い手はTh1とTc(細胞障害性T細胞)でありその機能発現にインタターフェロンγ(INF-γ)が重要な役割を担っている。胎児にはこのTh1とINF-γの機能が強く抑制されている。Th1の機能発現にはDC(樹状細胞)で産生されるIL-12が必要だが、この発現は強く抑制されている。さらにINF-γのプロモーターがメチル化されていることも知られている。INF-γが胎盤に働くと胎盤剥離がおこり、TNF-αが働くと流産にいたる(1)。このTh1の抑制は出産後もしばらく持続する。どのくらいの期間Th1機能が抑制されているかはまだ確定的な研究はない。当然遺伝学的な背景が大きく関与しており個体差が大きいと考えられる。新生児期にTh1の機能が抑制されている結果としてTh2優位に傾き易いことが乳児期早期に種々のアレルギー反応を起こす素因と考えられている。 乳児期早期にTh2に傾く機序が徐々に明らかにされてきた。昨年発表されたCulleyら(2)の論文によると生直後の新生児マウスに抗原を投与すると一次応答ではTh1もTh2もほぼ同じように増殖、分化するが、同じ抗原の二次刺激では抗原特異的Th1がアポトーシスをおこし、その後長くその抗原に対してはTh2が有意に増殖することがわかった。アポトーシスのシグナルはTh2から産生されるIL-4からTh1のレセプターを介して入ることが示された。IL-4レセプターからのシグナルはTh2の増殖、分化に必須のものとされ、Th1には影響を与えないものと考えられてきた。しかしIL-4レセプターはTh1にもTh2と同等に発現していることは知られており、その生物学的意義は不明であった。Th2のIL-4レセプターはcommonγと呼ばれる、他のサイトカインレセプターとの共通分子とヘテロダイマーの形で細胞表面に存在し、IL-4と結合することが知られている。しかしTh1細胞表面に表現されているIL-4レセプターはIL-13のレセプター(IL-13Rα1)とヘテロダイマーを形成していることが明らかにされた。そしてそのヘテロダイマーにIL-4のシグナルが入ると、アポトーシスに誘導されていくことがわかった。さらに重要な点は、このTh1へアポトーシスシグナルが入るのは生後6日以前に一回目の抗原刺激が行われた場合であり、6日目以降に抗原の一次刺激があればIL-13レセプターとのヘテロダイマーは形成されず、二次応答でも成人同様のTh1の増殖、分化が見られるのである。図からは2次刺激後のTh1におけるINF-γ産性能とIL-13Rα1の発現量が負の相関を示すことがわかる。このことは小児科の臨床で観察されている現象と一致する。牛乳抗原を出生早期より与ええると一部の小児に重篤なミルクアレルギーが見られること、早期にRSウィルス感染またはRSウィルスワクチン接種があるとRSウィルスに対して重篤な反応性気道過敏を起こすことが知られていた。RSウィルス感染に関してはマウスを使った実験で出生後早期に感染させると重篤な肺感染症をきたすのに対し、生後8日以降の感染では重篤な肺病変には至らないことが報告されている(3)。これらの動物実験の結果を待つまでもなく、新生児早期にアレルギーを起こしやすい食物抗原を与えてはならない、アレルギーの予防に除去食は重要であることは既に小児科臨床では確立した知見とされている。そのため一時期厳密な除去食がアレルギー予防の観点から重要であるとされた。母乳の微量抗原でさえ問題で、授乳中の母親は厳密な除去食が必要だとされた。しかしこれに関しては異論も多い。Verhasselt等の(4)の報告によれば母乳中に含まれるTGF-βが、母乳中に含まれる微量の食事抗原と一緒に哺乳されると食事抗原の耐性を誘導することが報告された。従来より母乳中にはTGF-βが多く含まれることが知られていたが、その生物学的意義は不明であった。この発見の意味することは大きい。動物が生存する為には多種類の食物を摂ることが基本的に重要であり、それがアレルギー反応により制限されるのは多くの不利益を生む。その解決策として母乳中のTGF-βが機能しているとすれば、極めて長い間に行われた進化の偉大さを改めて感じざるを得ない。ある時期の除去食の重要性に異論はないものの、一定時期を経過すれば除去食の必要はなく、牛乳抗原や卵白抗原にアレルギー反応を起こした幼児でもなんの問題もなくそれらの食物を摂取できることも確認されている。同時に必要以上長期の除去食の弊害も指摘されている。現在はどの時期に除去食を解除できるか、その目安となるバイオマーカーが何かが問われている。遺伝学的な背景が個々人で大きく異なり未だ統一的なものはなく、臨床現場で手探りの状態が続いている。今回その目安となる分子の一端が明らかにされたことの意義は大きいと考えられる。 免疫グロブリンの発見は臨床に早期から取り入れられ多くの疾患の病態解明、臨床のマーカーとして使用されてきた。それに反し細胞性免疫に関してはいまだ十分に臨床応用がされていないのが現状であろう。アレルギーの病態は多因子が複雑に関与している。IgEがアレルギーに大きく関与していることは紛れもない事実でありながら決してそれだけでアレルギーが発症するわけではない。Th2がアレルギーに関与していることも異論はないが、動物実験でみられる喘息モデルではTh1の関与がないと喘息が発症してこないことも知られている。複雑に多くの因子が絡んだ病態を解明するにはそれに関与する分子を一つずつ見つけていかなければならない。徐々にではあるがそれらの責任分子が明らかになりつつある。今回の発見はその中でも大きな意味を持つものと期待されている。 文献 (1) Ofer Levy. Innate immunity of the newborn: basic mechanisms and clinical correlates. Nature Reviews Immunology 7 379-390 (2007) (2)Hyun-Hee Lee , Christine M. Hoeman , John C. Hardaway , F. Betul Guloglu , Jason S. Ellis , Renu Jain , Rohit Divekar , Danielle M. Tartar , Cara L. Haymaker , and Habib Zaghouani. Delayed maturation of an IL-12 – producing dendritic cell subset explains the early Th2 bias in neonatal immunity. J. Exp. Med. Vol. 205 No. 10 2269-2280(2008). (3) Fiona J. Culley, Joanne Pollott, and Peter J.M. Openshaw. Age at First Viral Infection Determines the Pattern of T Cell–mediated Disease during Reinfection in Adulthood. J. Exp. Med., 196: 1381 - 1386. (2002). (4) Val|[eacute]|rie Verhasselt , Val|[eacute]|rie Milcent , Julie Cazareth , Akira Kanda , S|[eacute]|bastien Fleury , David Dombrowicz , Nicolas Glaichenhaus & Val|[eacute]|rie Julia. Breast milk|[ndash]|mediated transfer of an antigen induces tolerance and protection from allergic asthma. Nature Medicine 14, 170-175 (2008) | ||
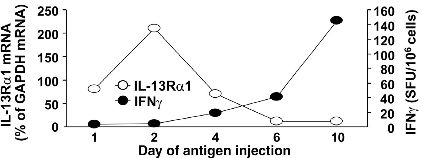 | ||
図.(2)より引用。生後1,2,4,6,10日後に初回免疫を行い2週間後に2回目の免疫を行った時のT細胞のインタフェーロンーγ産性能と、IL-13レセプター分子(IL-13Rα1)の発現量を示してある。両者が負の相関を示し、生後6日目がターニングポイントになっていることがわかる。
| ||